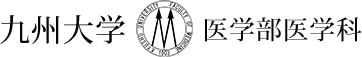2011.07.26
医学英語教育学会 植村研一賞インタビュー 「Service-Learning in Nicaragua」 医学教育学 KURAMOTO講師
 |
植村研一賞の受賞おめでとうございます。満場一致で受賞が決定したとお伺いしております。
受賞にあたりご感想をお聞かせいただけますか。
この「Service-Learning in Nicaragua」についてお聞かせいただけますか。
「Service-Learning in Nicaragua」は途上国である中米のニカラグア国に行き、医療ボランティアを行っているアメリカのNPO医療団体に加わり、ボランティア活動をとおし て、異国間コミュニケーションや医療の必要性を学び、英語を活用することを目的とした教育プログラムで、平成23年度から九州大学医学部では総合医学の1単位として認められています。私は2007年に九州大学に赴任し、「学生が短期で海外に渡航し英語を使えるような教育プログラムを創造して欲しい」と依頼されました。そこで、英語圏の国や医学教育を英語で行っている国など30カ国くらいの大学にコンタクトしたのですが、どの大学も「入学すれば受け入れてもよい」との回答ばかりでした。次にService-Learning※ を行っているアメリカの大学に参加することを試みたのですが、アメリカの大学は911のテロ以来、海外への警戒心が強く、快諾してくれるところはありませんでした。
そんな中、思い出したのが看護師をしているアメリカの友人のことです。その友人は7年前からNPO医療団体のニカラグアのボランティアに参加しており、相談してみたところ、そのNPO医療団体を紹介してくれました。そこで、2009年にパイロットスタディ※ として、まず私自身が参加し、特に学生が参加した場合、安全性が確保されているかなど、現地の状況を確かめました。そして、2010年に九大の学生4名を、2011年に他大学3名を含む8名の学生を参加させることができました。
実はパイロットスタディには私と夫、子供2人の4人で参加したのですが、それは人の親として子供の本当の教育には、世界の現状を見る必要があると思ったからでした。同時に自分の子供を参加させることができたので、自信を持って安全だということが確認できました。 このNPO医療団体では、ボランティア参加者全員が、ニカラグア国発行の短期の医療ライセンスを取得することで、ボランティア参加者が法的なトラブルに巻き込まれることを防いでおり、その観点からも安全で信頼できる団体だといえます。
この「Service-Learning in Nicaragua」は、私が現地でサポートできるので、英語のスキルに自信のない学生、海外やボランティアに馴染みのない学生にもお勧めです。入門編とでもいいましょうか、まず自分でどこかに参加するより先に、この「Service-Learning in Nicaragua」に参加して欲しいと思います。
※Service-Learning …大学・学校の教科で学習したことを活用し、社会改善活動に援用する授業論。市民的責任、自尊感情、コミュニケーション能力などを高めることを目的とする。
※パイロットスタディ…試験的な調査
ニカラグアの医療状況はどのような感じなのでしょうか。
 |
|
| 教会の建物を借りて開かれたクリニック |
このため、私たちが参加したNPO医療団体は製薬会社などから寄附をつのり、ニカラグアに薬を運んでいます。そして、医師、薬剤師のボランティアにより年に 5-6回、医療の行き届いていない山間部の学校や教会、時には馬小屋などの建物を借りて、期間限定のクリニックを開設しています。期間前に整理券を日本円で10円くらいの金額で販売するのですが、購入できない人には無料で配布します。これは、来院する人の数を把握し、期間中診察が円滑に進むようにするためです。その整理券で集まったお金は、現地で井戸を掘る資金などに役立てられ、現地の人にそのまま還元されます。
具体的に参加した学生は現地でどのような活動をするのかをお聞かせいただけますか。
 |
|
| 診療する医療者につき学びます。NPOに参加する医療者は教える 気持ちが強く熱心にご指導されていました。 |
寮に戻ってからはNPO医療団体のディレクターや医師の方からの英語での講義を受け、ディスカッションをすべて英語で行います。ニカラグアの経済状況や医療状況、病症としては寄生虫が多いのですが、その理由を学んだりします。 宿題として、英語で考えた質問を、通訳をとおして現地の人に答えてもらい、質問した事項とその答を文書としてまとめたり、政治家や他のNPO医療団体、製薬会社へ支援を求める手紙を書いたりしました。
「Service-Learning in Nicaragua」に参加後の学生の意識の変化などをお聞かせいただけますか。
現地では毎日英語で日記を付けてもらいますが、日記を読むと成長したなと思います。日本の医療システムの長所を理解し、世界への責任を感じるようになるようです。ずっと中耳炎を患わっていた子供が診察を受け、抗生物質を飲むと、わずか一週間くらいで完治するんですね。日本国内だったら普通のことなんですが、その子供にとっては、人生が変わるくらいの大きな出来事です。簡単なことなのに、そんな治療が受けられない所があるという現実を痛感するようです。同時に、ボランティアスピリットも身につくようで、2011年の参加者の中には、帰国後に東北にボランティアに行った学生もいます。一度でもこのような経験をすると、自尊感情を高めることができ、自分にも何かできることがあると行動できるようになっています。 |
 |
 |
| 待合いでの血圧検診 | 医療者の指導の下 診察を行います。 | 診察を待つ子供に風船をプレゼント |
| ....More こちらからスライドショーをご覧いただけます。 | ||
学生にむけてメッセージをお願いいたします。
 |
私たちが最近渡航したのは2011年3月12日でした。東日本大震災の翌日です。出発の時はこんなに甚大な被害とはわからないまま現地に行きまし た。もちろん、現地では十分な情報が得られませんでしたので、帰国後にあまりの甚大な被害に驚愕しました。感動したのは、ニカラグアの多くの人に「地震は大丈夫?日本のために祈っています」と声を掛けられたことです。持たざる国の人がこんなに祈ってくれるのに、すべて持っている私たちが他の国に知らん顔などできないと思います。九州大学の学生にも、そう感じて欲しいと思っています。
 |
「Service-Learning in Nicaragua」には、2010年には九州大学の学生のみでしたが、2011年には山口大学、佐賀大学、日本大学からも参加されています。クラモト先生は、より多くの人がこのニカラグアでのボランティア活動に参加し、この活動が永く続くことを願っているそうです。
2012年の渡航予定は3月16-24日です。もっと知りたい方は
クラモト先生 christi(a)edu.med.kyushu-u.ac.jp ((a)を@に読み替え)にご連絡を!